
ちゃんと伝えたのに、なぜやってくれないんだろう?

説明したはずなのに、全然違うことをしている
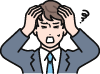
何度言っても伝わらない
リーダーや上司なら、一度は感じたことがある悩みではないでしょうか。とくに中小企業では、ひとりの判断ミスや誤解が業務全体に直結するため、「いかに正確に伝えるか」は組織運営の生命線とも言えます。
しかし、ここで立ち止まって考えたいのは、「伝える」と「伝わる」はまったく別物だということです。
上司が「伝えた」と思っているのは、「自分が話した・指示した・説明した」という行為にすぎません。一方で「伝わる」とは、相手がその意図を理解し、行動に反映している状態です。つまり、伝える側ではなく、受け手の行動で判断されるものなのです。
ところが多くの職場では、上司が「伝えた」で安心し、部下は「聞いたけど、どうすればいいのかまではわからなかった」というズレが生じています。この小さな認識の差が、やがて「動かない部下」「理解の浅い社員」という誤解を生むのです。
本コラムでは、上司の“伝え方”のどこに落とし穴があるのかを整理し、相手に本当に届く“伝わる指示”に変えるための具体的な視点を紹介します。
「伝える」と「伝わる」は違う ― コミュニケーションの構造
多くの上司が「伝えたのに、なぜ動かない?」と感じる背景には、そもそも「伝える」と「伝わる」を混同していることがあります。
この2つの違いを理解しないままでは、いくら指示の回数を増やしても効果は上がりません。
「伝える」は行為、「伝わる」は成果
「伝える」とは、言葉やメールで情報を発信する行為です。
一方の「伝わる」は、相手がその意図を理解し、行動に反映できた状態を指します。
つまり、伝えること自体はスタートであり、伝わるかどうかはゴールなのです。
ところが多くの上司は、「話した=伝わった」と思い込んでしまいます。話した内容よりも、「相手がどう受け取ったか」「どう動いたか」を確認する姿勢が欠けているのです。
伝わらないのは、部下の理解力の問題ではない
「何度言ってもわからない」「説明しても理解しない」――
こうした不満の裏側には、“受け手の問題”にしてしまう構造があります。しかし実際には、上司の伝え方に“理解を妨げる要素”が潜んでいることが少なくありません。
たとえば、以下のような状況です。
- 指示が抽象的で、ゴールが見えない
- 背景や理由が省略されており、判断の基準がわからない
- 一方的に伝えて終わりで、確認の機会がない
これでは、部下が「わかったつもり」で動き出しても、ズレが生じるのは当然です。つまり、「伝わらない原因の多くは伝える側の設計不足」にあります。
「伝える」から「設計する」へ
本来、上司の役割は指示を出す人ではなく、行動を設計する人です。
部下がどう受け取り、どう動くかを想定したうえで言葉を選び、順序立てて伝える――これが伝わるコミュニケーションの基本構造です。
言葉は一方通行ではなく、相手の理解を前提に組み立ててこそ意味を持ちます。「伝える」ことに満足せず、「伝わる」までを仕事とする。その意識の転換こそが、上司に求められる第一歩です。
上司がやりがちな伝わらない3つの癖
「伝えているのに伝わらない」背景には、部下の理解力ではなく、上司側の伝え方にパターン化された癖があることが多くあります。
ここでは、職場で特によく見られる3つの癖を紹介します。
①抽象的な言葉を使ってしまう
「しっかりやっておいて」
「できるだけ早めに」
「もう少し丁寧に」
これらは職場で頻繁に使われる言葉ですが、具体的に何を指すのかは人によって異なります。上司の頭の中では明確なイメージがあっても、部下には基準が見えません。
たとえば「早めに」と言われても、上司が想定するのは今日中、部下の感覚は今週中ということも珍しくありません。
このような抽象語は、認識のズレを生む最大の原因です。
伝えるときは、「いつまでに」「どの状態まで」を明確にすることが重要です。つまり、評価できる言葉で伝えること。
「早めに」ではなく「今日の17時までに」、「丁寧に」ではなく「誤字脱字がないようにチェックして提出」と、相手が行動に移せるレベルまで具体化しましょう。
②背景や目的を省いてしまう
上司が自分の中で「なぜそれをやるのか」を理解していても、それを共有しないまま指示を出してしまうケースは少なくありません。
しかし、人は目的を理解していないと、行動の優先順位を正しく判断できません。
たとえば「明日の会議資料を修正しておいて」と伝えたとき、その理由が「社長に提出する最終版だから」なのか、「まだたたき台の段階だから確認用なのか」で、力の入れ方や仕上げ方がまったく変わります。
目的を伝えることは、相手に判断の基準を渡すことでもあります。
背景を共有すれば、上司の意図を先回りして考える社員が増え、結果的に上司の指示の手間も減っていきます。
③確認をせずに終わらせてしまう
会話の最後に「わかった?」と聞くだけでは、確認にはなりません。多くの部下は、理解していなくても「はい」と答えてしまいます。
伝わるコミュニケーションに必要なのは、理解の再確認です。
たとえば、「じゃあ、今の内容を簡単にまとめてみて」と返させたり、「どう進める予定?」と聞いてみたりしましょう。部下の言葉で説明させることで、初めて理解の程度が見えてきます。
さらに、伝達後のフォローも大切です。
進捗を一度確認するだけで、「聞いたけど忘れた」「勘違いしていた」といったミスを防ぐことができます。伝えることと、伝わることの間にある確認の一手間が、職場の精度を大きく変えるのです。
伝わる指示をつくる3つのステップ
ここまで見てきたように、伝わらない原因の多くは、上司の側にあります。
では、どうすれば伝えた内容が相手に正確に理解され、行動につながるのか。そのカギとなるのが、伝え方を設計するという意識です。
ここでは、伝わる指示をつくるための3つのステップを紹介します。
【ステップ1】目的を伝える
最初に必要なのは、何をしてほしいかよりも、なぜそれをするのかを伝えることです。目的が共有されていなければ、部下は表面的な指示にしか反応できません。
たとえば「顧客リストを整理しておいて」と言われたとき、それが「来期の営業方針を立てるため」なのか、「今後のDM発送を効率化するため」なのかによって、作業の優先順位も判断基準も変わります。
上司が目的を明確に伝えることで、部下は自分の役割を理解し、行動の背景を踏まえた判断ができるようになります。
【ステップ2】期待する成果を示す
次に重要なのは、どの状態になれば完了かを具体的に示すことです。これは「上司が頭の中で描いている完成形」を、言語化して共有するプロセスです。
「できるだけ早く」「丁寧に」ではなく、「今週金曜までに10件のリストを提出」「誤字脱字ゼロで完成」など、誰が見ても同じ基準で判断できるようにします。
また、完成イメージを共有することで、部下は「どの程度の質を求められているのか」を把握でき、無駄な修正や確認が減ります。
伝える側にとっても、期待値を明文化することで、評価やフィードバックがしやすくなります。
【ステップ3】理解を確認する
最後のステップは、相手が本当に理解しているかを確認することです。
多くの上司が「説明したから大丈夫」と思い込みますが、実際には、話を聞いても理解できていないケースが多くあります。
確認といっても、「わかった?」と尋ねるだけでは不十分です。
部下に「では、どう進めるつもり?」「今の内容を自分の言葉でまとめてみて」と問い返し、相手の理解を言葉で確かめることが大切です。
このプロセスによって、上司は部下の認識のズレを早期に発見でき、部下にとっても「理解したつもり」を防ぐ学びの機会になります。
伝わる指示をつくるポイントは、話す量ではなく、伝える順序にあります。目的を伝え、期待する成果を明確にし、理解を確認する。この3つを意識するだけで、上司の言葉は格段に届きやすくなります。
伝わる力を組織に根づかせるには
上司一人の努力で伝え方を改善しても、組織全体のコミュニケーションが変わらなければ、すぐに元に戻ってしまいます。
伝わる力を育てるには、上司だけでなくチーム全体が「伝わり方」に意識を向ける文化をつくることが大切です。
伝えた側が責任を持つ文化をつくる
多くの職場では、「言われたことをやっていない」「ちゃんと聞いていない」と、受け手の責任を問う場面が多くあります。しかし、本来の責任は伝えた側にもあります。
相手が理解できていないなら、それは伝え方が不十分だったというサインです。
上司が「自分の伝え方を改善する」姿勢を見せることで、部下は安心して質問や確認ができるようになります。伝える側が主導してコミュニケーションの質を高めていく。この意識が定着すると、組織全体の誤解や行き違いは大幅に減ります。
確認と共有の仕組みを設ける
伝達を個々の判断に任せると、どうしても抜け漏れが生じます。そのため、確認と共有の仕組みを業務の流れに組み込むことが有効です。
たとえば、
- ミーティング後に要点を3行でチャットにまとめる
- 指示を受けたら、部下が「理解した内容」を返信で確認する
- 報告書には「判断の背景」も1行添える
こうした小さなルールを習慣化するだけで、伝達の精度は格段に上がります。
仕組みをつくる目的は、監視ではなく誤解を防ぎ、理解を深めるための補助輪だということを共有することが重要です。
聞く力を育てる
伝える力と同じくらい大切なのが、聞く力です。いくら上司が工夫しても、相手が「聞く姿勢」を持たなければ伝達は成立しません。
部下にとっても、「何を意図してこの話をしているのか」「どこまでを自分の判断で動けるのか」を意識して聞く力を磨くことが求められます。
上司は、「質問してもいい」「理解できないことをそのままにしない」雰囲気をつくることで、双方向のコミュニケーションを促せます。
伝わる力を組織に根づかせるということは、一方的な指示の文化を、対話と理解の文化に変えることです。
指示が通じないときこそ、上司の言葉と姿勢が問われます。
まとめ ― 伝えるとは、相手の行動を設計すること
「ちゃんと伝えたのに」「説明したはずなのに」
そう感じるとき、上司はつい部下の理解力や集中力を疑ってしまいがちです。けれど、伝わらない理由の多くは、伝えた内容ではなく、伝え方の設計にあることを忘れてはいけません。
伝えるとは、単に情報を渡すことではなく、相手の行動を設計することです。
相手がどんな状況で、どんな前提を持っていて、どう受け取るかを想定したうえで伝える。その設計があるからこそ、言葉が意味を持ち、行動につながります。
上司が「伝えた」で終わらせず、「どう受け取られたか」「どう動いたか」まで責任を持つ姿勢を見せれば、
部下も「自分が理解するまで確認していい」と感じるようになります。
伝える力は、上から下への一方通行ではなく、信頼を土台とした双方向のコミュニケーションによって育つものです。
忙しい職場では、どうしても効率を優先して、伝える内容を省略しがちです。しかし、伝わらないまま進めることで起きるやり直しや誤解のほうが、はるかに大きなロスになります。伝えることに丁寧さを取り戻すことが、結果的に組織の生産性を高める近道なのです。
伝えたつもりをやめ、伝わることに責任を持つ。
それが、リーダーとして最も基本であり、最も難しいマネジメントスキルです。明日からの会話の中で、ひとつでも「伝わるための工夫」を意識してみてください。
その積み重ねが、組織全体のコミュニケーションの質を確実に変えていきます。
「うちの職場も同じかもしれない」
そう感じた方は、ぜひお気軽にご相談ください。日々の“ちょっとした伝わらなさ”を見直すだけで、
チームの雰囲気も成果も驚くほど変わっていきます。
現場に合った伝え方や関わり方の工夫を、一緒に考えていきましょう。

