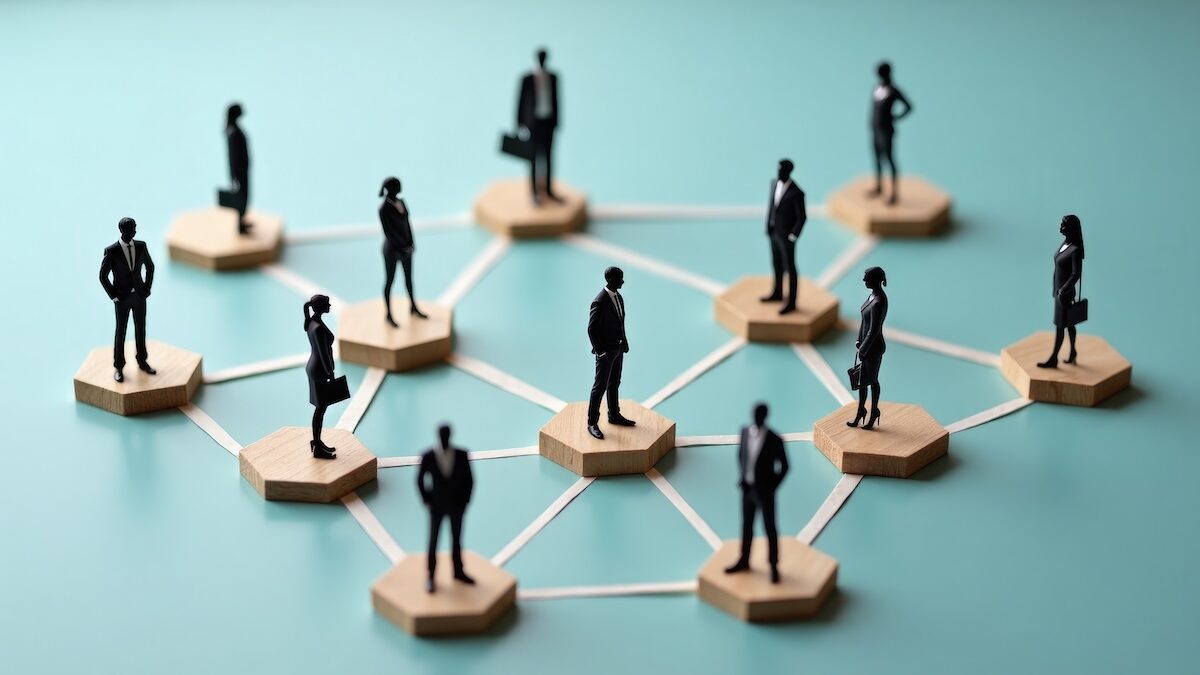「評価制度を導入したのに、なぜか職場の雰囲気が悪くなった気がする」
そう感じている経営者・人事担当者の方はいないでしょうか。
社員同士の会話が減り、チーム内での助け合いも少なくなり、それぞれが自分の仕事だけに集中しているように見える。
制度としては間違っていないはずなのに、職場にピリピリした空気が流れ始めている──そんな違和感を抱く会社があります。
背景にあるのは、「個人評価」を重視しすぎた評価制度です。
たしかに、個人の成果や能力を正しく評価する仕組みは必要です。ですが、その一方で「チームで働く」「協力し合う」という組織の土台が崩れてしまえば、制度の本来の目的──組織全体の力を高めること──にはつながりません。
本コラムでは、「個人評価がチームワークを壊す」構造と、そこから抜け出すための制度設計・運用の視点について整理します。
協力より自分の成果を優先する行動の例
評価制度が個人の成果に偏りすぎると、社員は評価されるために協力よりも成果の見える化を優先し始めます。
本来、組織は個人の強みをいかし、弱みを補完し合うことで、全体の成果を量・質共に増やすことが目的です。しかし、制度が個人単位での数値評価や成果を重視するように設計されていると、次のような行動が職場に広がりやすくなります。
- 業務のノウハウや工夫を共有しない
- 同僚のミスをカバーせず、黙って見過ごす
- 困っている人がいても、自分の仕事を優先する
- 他部署との連携を避け、関与範囲を最小限にとどめる
- 成果をアピールする行動は活発だが、裏方の支援は敬遠する
このような状況が続くと、個々のパフォーマンスは一見保たれているように見えても、チームとしての生産性や職場の一体感が明らかに低下していきます。
また、協力行動が評価の対象にならなければ、誰かを助けることは損とみなされるようになります。結果として、周囲に目を向けず、自分の成果だけに注力する社員ばかりの職場ができあがってしまうのです。
その空気はやがて、新人や業務に不慣れな人材にとって非常に厳しいものとなります。助けてもらえず、相談しにくく、孤立感を深める。こうした環境では、育成もうまくいかず、離職リスクも高まります。
一人ひとりが頑張っているはずなのに、組織としてはバラバラになってしまう。
それは、制度が個の成果だけに報いる構造になっているからかもしれません。
協働が軽視されると、チームとしての成果が上がらない
組織である以上、目指すべきは「個人の足し算」ではなく「掛け算」です。
しかし、評価制度が個人の目に見える成果だけを評価軸にしていると、協働の重要性が組織全体で軽視されるようになります。
たとえば、ある部署では全員が自分の業績目標だけを追い、他部署の応援や社内連携に時間を使うことが「損」だと認識されていたとします。すると、部署をまたいだプロジェクトや共通課題への取り組みは後回しになり、組織としての統一感やスピード感が著しく損なわれます。
また、こうした環境では調整役やつなぎ役といった見えにくい貢献が評価されず、重要な役割を担っている人が報われなくなるという副作用も生じます。これはモチベーション低下だけでなく、将来的な人材流出にもつながりかねません。
協働やチームワークは、成果が直接見えにくいからこそ、制度として明示的に評価の対象にする必要があります。
たとえば「他部署との連携への貢献」「チーム内での情報共有」「後輩への支援や育成」などを評価項目に加えることで、組織としての一体感と成果を両立させる方向へ舵を切ることができます。
評価制度の見直しは、組織文化の再設計でもあります。
個人が互いに支え合いながら成果を出せる環境こそ、持続的な組織力の源になるのです。
チーム視点にシフトする評価制度──協働を促進する3つの仕組み
評価制度が個人主義を助長してしまうならば、その逆もまた可能です。制度の設計と運用次第で、組織全体に協働の文化を根づかせることは十分にできます。
ここでは、評価制度を個人主義的な設計からチーム視点へとシフトさせるために有効な3つの仕組みを紹介します。
協働行動そのものを評価項目に加える
個人の成果だけでなく、チーム全体への貢献も評価対象に加えることが重要です。たとえば、自身の担当業務の成果に加え、
- チーム内での情報共有や助言
- 業務改善の提案
- 他のメンバーのフォローや教育
- 他部署との協働の推進
といった行動を評価項目として組み込みます。
こうした行動は一人で完結する成果ではなく、周囲との関係性の中で生まれるものです。それらに光を当て、評価の中に明示的に含めることで、個人プレーよりもチームとしての成果を意識する文化が醸成されます。
また、「周囲が安心して相談できる」「ミスや問題を早めに共有できる雰囲気をつくる」といった心理的安全性を高める行動も、チームの力を底上げする重要な要素です。人間関係の潤滑油となる存在や、裏方的な働きも評価の中で可視化される仕組みが必要です。
チーム目標と個人目標をセットで設計する
評価制度を設計する際、個人目標だけでなく、チームや部門単位での共通目標を設定し、一定割合を評価に反映させる方法が効果的です。
もしくは、個人目標を設定する際に、チームや部門への貢献を重視した内容にすることも有効です。
これにより、個人がチーム全体の成果にも意識を向けるようになります。チーム内での支援や連携が「評価される行動」として明確になるため、個人の数字だけに固執する姿勢を抑えやすくなります。
特に営業や販売など、個人実績が前面に出やすい職種においては、チーム成果の指標を加えるだけで行動が変わることもあります。
面談で「他者との関係性」にも目を向ける
評価制度を望ましい行動を増やす育成のツールとして捉え直すことで、チームの方向性がそろい、組織の土台が強化されます。
そのためには、目標設定やフィードバック面談の中で、周囲との連携について問いかけることが有効です。
たとえば、面談時に次のような質問をしてみましょう:
- 誰と協力して仕事を進めたか?
- 他のメンバーと良い連携がとれた場面は?
- チームとして成果を出すために意識したことは?
こうした問いかけを繰り返すことで、評価の観点が個人からチームへと拡張されていきます。協力すること、学び合うこと、成果をチームで最大化することが、自然と評価される文化が育ちます。
協働型評価がもたらす組織の変化
チーム視点を取り入れた評価制度は、単に公平性を高めるだけでなく、組織の文化そのものを変える力を持っています。ここでは、協働を促す評価制度がもたらす3つの変化を紹介します。
信頼と心理的安全性が高まる
協力することが評価される環境では、自然とお互いに手を差し伸べる行動が生まれます。
これにより、メンバー同士の信頼感が育ち、ミスや課題も共有しやすい風通しの良い職場ができていきます。
心理的安全性が高まると、社員は失敗を恐れずチャレンジできるようになり、結果として学習と成長のスピードが加速します。
組織の一体感が生まれやすくなる
個人の達成ではなく、チームや部署全体で成果を出すことが評価されると、目線が自然と組織全体に向きます。
目標の共有や協働の促進、部門間の壁を越えた連携が進みやすくなり、一体感のある組織風土が醸成されていきます。
また、新人や中堅、ベテランといった立場の違いを超えて、「一緒に成果を出す」という共通目的が意識されやすくなるのも大きなメリットです。
自律的に動ける人材が育つ
チームへの貢献や協働のプロセスが評価されると、指示待ちではなく、自ら考えて動く社員が増えていきます。
「誰かの役に立ちたい」「チームの成果を高めたい」という動機が、行動の原動力になっていくからです。
このような人材が増えることは、組織にとって持続的な成長エンジンを手に入れることと同義です。つまり、協働型の評価制度は、個人のやる気だけでなく、組織全体の活力と未来を支える仕組みなのです。
まとめ
人事評価制度は、個人の成果を測るだけの仕組みではありません。組織が大切にしたい価値観や行動を形にし、それを育む装置です。
もし制度が、個人の数値目標だけに偏っているなら、協働が損なわれ、組織の推進力を弱めてしまう可能性があります。一方で、制度の中に「協力する」「連携する」といった行動の価値を組み込むことができれば、評価制度はチームの力を引き出すツールになります。
- 協働そのものを評価に入れる
- チーム目標を評価に組み込む
- 面談で関係性に光を当てる
これらの工夫は、すぐにでも着手できる実務的なアプローチです。
評価制度は、制度としての正しさだけでなく、現場の行動をどう変えるかという視点で見直すことが大切です。今一度、評価項目や運用プロセスが、組織にとって本当に望ましい行動を後押しできているか、点検してみてはいかがでしょうか。