人事評価制度を導入したものの、実際にはうまく機能していない──そんな声を中小企業からよく耳にします。

「評価シートはあるけど、ほとんど使われていない」
「制度はあるけど、年に一度の査定のときに形式的に使うだけ」
こうした形骸化のケースは決して珍しくありません。
一方で、こんな声も聞かれます。
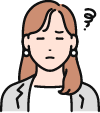
「評価項目が多すぎて、評価するだけで半日かかる」
「シートは埋めるけれど、正直ここまで細かくやる必要があるのか疑問」
こちらは制度が複雑すぎて負担になっているケースです。形骸化しているわけではないものの、評価にかかる労力が過大で、現場から不満や疲弊感が生まれてしまいます。
つまり、評価制度は「形骸化して機能していない」か「複雑すぎて疲弊する」かの両極端になりがちです。どちらのケースでも共通しているのは、制度が現場に根づいていないということです。
では、現場で実際に使い続けられる評価制度とは、どのようなものでしょうか。
評価が形骸化・複雑化する3つの原因
評価制度が現場で根づかない背景には、いくつか共通する原因があります。ここでは、形骸化や過剰な負担を招く典型的な3つのパターンを整理します。
評価項目が多すぎる
「制度をしっかり作ろう」と意気込みすぎた結果、20項目以上もの評価項目や5段階以上の評価軸を盛り込んでしまうケースがあります。
確かに網羅性は高まりますが、現場では書くだけで疲弊し、運用する余力がなくなるのが現実です。
評価の目的が曖昧
評価は何のために行うのか──処遇のためなのか、育成のためなのか、あるいはその両方なのか。ここが不明確なまま制度を設計すると、評価者も被評価者も納得感を持てません。
結果として「とりあえずシートを埋めるだけ」「何を意識して取り組めばいいのか分からない」といった形骸化を招きます。
評価と処遇がつながっていない
せっかく評価をしても、その結果が昇給や昇格などの処遇に結び付かないと、現場からは「やっても意味がない」と見なされがちです。
また、処遇と切り離して「育成のため」と説明しても、評価と日常のフィードバックが連動していなければ、やはり実感は伴いません。
シンプルな評価制度にするための工夫
評価制度を機能させるカギは、いかにシンプルに設計するかにあります。網羅性や理想を追求しすぎると、現場では使いこなせず、結局は形骸化や疲弊を招いてしまいます。ここでは、制度をシンプルに整えるための3つの工夫を紹介します。
評価項目を絞り込む
評価項目は10〜15項目程度に収めるのが現実的です。
「できれば入れたい」を全部盛り込むのではなく、会社として「今」本当に評価したい行動や成果だけに厳選することが重要です。
シンプルにすることで、評価者も被評価者も集中しやすくなり、制度として運用しやすくなります。
評価の目的を明確にする
評価制度の目的を明確にし、会社全体で意識を合わせましょう。従業員の誰に聞いても同じ答えが返ってくることが理想です。
例えば弊社の提供する傍楽式人事制度では、評価制度の目的を業績向上と人材育成に絞っています。一般的に言われる処遇をメインの目的としていません。
目的がはっきりしていれば、評価を受ける側も「何を意識すればよいか」を理解しやすくなり、納得感が高まります。
処遇との連動を分かりやすく設計する
評価制度は業績向上や人材育成が目的であれば、必ずしも処遇と連動させる必要はありません。実際、弊社では連動させていませんが、有効に機能しています。
しかし、一般的に処遇と連動させることが多いのが現実です。その場合は、評価と処遇の連動をわかりやすく設計する必要があります。
たとえば、評価ランクごとに昇給幅を定める、一定以上の評価で手当が支給される、といったルールを明文化します。
「評価が給与やキャリアに直結する」ことが見えると、制度は一気に現場に浸透しやすくなります。
現場で使い続けるための仕掛け
評価制度は設計して終わりではなく、現場で使い続けてもらう工夫が欠かせません。どれだけ優れた仕組みでも、現場で動かなければ意味がありません。ここでは、制度を定着させるための3つの仕掛けを紹介します。
定期的に見直す仕組みを持つ
制度は一度つくって終わりではなく、運用して初めて改善点が見えてきます。
「毎年1回、人事と現場リーダーが制度を振り返る」「アンケートで社員の声を拾う」といった仕組みを持ちましょう。
定期的な見直しがあると、制度は硬直化せず、現場に合った形に育っていきます。
面談を仕組みに組み込む
評価の納得感を高めるには、結果を伝えるだけでなくプロセスでの対話が重要です。
期初に目標設定、期中に進捗確認、期末にフィードバック──こうしたサイクルを制度の一部にしてしまいましょう。
短時間でも定期的に面談を行うことで、評価基準が現場に浸透し、社員も「何を頑張ればよいか」が見えやすくなります。
現場の声を反映する仕組みをつくる
制度を運用するのは現場です。現場の納得感がなければ、制度は絵に描いた餅になってしまいます。
「管理職やリーダーを巻き込んで評価項目を検討する」「運用上の不満を吸い上げ、次の見直しに反映する」といった工夫で、自分たちの制度だという当事者意識を醸成することができます。
まとめ
評価制度は、完璧さよりも現場で使えるシンプルさが重要です。
複雑すぎる制度は形骸化を招き、形骸化を避けても負担が大きすぎれば結局は運用が続きません。
- 評価項目を絞ること
- 目的を明確にすること
- 処遇との関係を整理すること
- 定期的な見直しと対話を仕組みにすること
これらを徹底するだけで、評価制度は現場に根づき、社員の成長や組織力の向上につながります。
人事評価制度は「立派なシートを作ること」が目的ではなく、社員の行動を導き、組織の成果を高めるための道具です。
だからこそ、まずは複雑さを取り払い、シンプルで使い続けられる制度づくりを目指しましょう。

