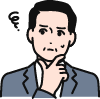
バックオフィスのスタッフをどう評価すればいいのか分からない
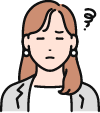
店舗のサポート業務は成果が見えづらく、頑張りを数字で表せない
中小企業の人事制度づくりを支援していると、こうした相談を非常によく受けます。
営業や販売などの成果が数値で表れる職種に比べ、経理・総務・人事・事務、あるいは店舗の裏方業務やサポート業務のような職種では、成果が見えにくい・評価しづらいという悩みがつきものです。
このような職種では、ミスを防ぐ・トラブルを未然に防ぐ・誰かを支えるといった目立たない貢献が多く、成果を単純に数値で測ることができません。
そのため、上司の感覚や印象に頼るなんとなく評価になってしまうケースも少なくありません。
しかし、見えにくいだけで、価値が低いわけではないのです。むしろ、そうした職種が安定して機能しているからこそ、営業や現場が成果を上げることができています。
では、こうした成果の見えにくい職種を、どのように評価制度の中で正当に評価していけばいいのでしょうか。
成果が見えにくい理由
成果が見えにくい職種には、いくつか共通する構造的な理由があります。ここでは、特に中小企業で多く見られる3つの要因を整理します。
数値化しにくい業務が多い
営業職のように売上や契約数で評価できる職種と違い、バックオフィスやサポート職は日々の業務が定量化しにくい傾向があります。
経理であれば「請求ミスを防いだ」、総務であれば「社内ルールを整えた」など、成果はあるものの「何件処理した」だけでは本質を測れないのです。
成果が他者の成功に埋もれやすい
サポート職の成果は、自分ではなく他の誰かの成果につながる形で現れます。
たとえば、営業が安心して提案できるのは、正確な事務処理や在庫管理が支えているからです。しかし、その貢献は「間接的」なため、目に見える結果として認識されにくいのです。
「問題が起きないこと」自体が成果になっている
労務、経理、品質管理、店舗運営などでは、トラブルを防ぐことこそ最大の成果です。
ところが、問題が起きない=成果が見えないというジレンマがあり、安定運用を支えている人ほど評価が上がりにくくなってしまいます。
こうした理由から、見えにくい職種の評価は「成果をどう測るか」よりも、「貢献をどう見つけるか」という発想に切り替える必要があります。
見えない成果を見える化する3つの視点
成果が数値で表れにくい職種でも、視点を変えれば評価の材料は必ず見つかります。ここでは、実務で使いやすい3つの切り口を紹介します。
プロセス評価を重視する
結果だけでなく、日々の仕事の進め方(プロセス)の評価を重視します。
たとえば、期限を守っているか、報連相を適切に行っているか、ミスが発生した際に原因を整理し、再発防止を図っているかなど、行動として表れる部分を具体的に評価します。
プロセス評価を重視することで、成果だけでは見えにくい日常の努力や改善姿勢を認めることができ、社員の成長意欲を引き出すことにもつながります。
職務の目的を明確にする
職種ごとに、「何のためにこの仕事をしているのか」という目的を定義することで、評価の軸がはっきりします。
たとえば、経理であれば会社のお金の流れを正確に保つこと、総務であれば働きやすい環境を整えること、人事であれば組織全体の成果を高める人材を育てることが目的になります。
目的を明確にした上で、その達成度を基準に評価することで、「何をすれば貢献になるのか」を社員自身も理解しやすくなります。
貢献の“先”で評価する
成果を自分の中で完結させず、どの成果や誰の成果に貢献したのかという視点で評価します。
たとえば、営業担当がスムーズに提案できたのは、事務スタッフが正確な在庫情報や見積データを迅速に提供したからかもしれません。この場合、事務スタッフ自身の数値成果は見えにくくても、営業部門の成果に明確に貢献していると言えます。
では、営業部門の成果への貢献度をどのように測ればよいでしょうか。具体的には、次のような観点が考えられます。
- 依頼対応のスピード(リードタイム):営業からの依頼に対して、どれだけ早く正確に対応できたか。
- ミスや差戻しの発生率:見積や在庫データの誤りがどれだけ少なく、営業活動を滞らせなかったか。
- 他部署からの満足度・信頼度:営業部門が事務スタッフの対応をどの程度「頼りになる」と感じているか。
- 改善・提案の実施状況:営業活動の効率化につながる提案や改善を自ら行っているか。
これらの指標を通じて、事務スタッフの仕事が営業成果の質やスピードにどう影響しているかを見える化することができます。
また、部門の成果への貢献度という視点を持つことが有効です。
通常、会社全体の売上や利益といった最上位の成果や目標をベースに、それを支える各部門の成果や目標を設定します。
その上で、自分の業務が部門の成果や目標にどの程度貢献したかを評価の基準とします。
こうした考え方を取り入れることで、評価が抽象的な“がんばり”ではなく、具体的な成果への貢献として可視化されます。
同時に、社員が自分の業務と組織全体の方向性を結びつけて考えられるようになり、組織全体の一体感と自律性が高まります。
定性評価を主観で終わらせない工夫
成果が見えにくい職種では、どうしても「頑張っていると思う」「しっかりやっているように見える」といった上司の印象で評価が決まりがちです。
しかし、このような印象評価(感覚評価)は、評価の納得感を下げるだけでなく、社員のモチベーションを大きく損なう原因にもなります。
ここでは、定性評価を主観で終わらせず、客観性と再現性を高めるための3つの工夫を紹介します。
行動基準を言語化する
「頑張っている」「協力的だ」といった抽象的な言葉のままでは、評価者によって解釈が異なります。
そこで、評価したい行動を誰が見ても同じ基準で判断できるように具体化することが大切です。
たとえば、
- 「主体的に行動している」→「指示を待たず、自分から改善点を提案している」
- 「チームワークが良い」→「他のメンバーの業務を理解し、必要に応じてサポートしている」
といった形で、行動として観察可能な表現に変換します。この工夫だけでも、評価のバラつきが大幅に減り、面談での説明も明確になります。
複数の視点で評価する
一人の上司だけが評価する仕組みでは、どうしても主観が入ります。
そこで、複数の評価者による相互確認(クロスチェック)を取り入れることで、公平性を高めることができます。
たとえば、上司同士で評価結果を共有し、評価の根拠を説明し合う「評価者会議」を設ける方法があります。
また、チーム内のメンバーや他部署からのフィードバックを一部取り入れる「多面評価」も効果的です。
特に間接部門やサポート職では、日常的に関わる他部署の意見を取り入れることで、現場感のある評価が可能になります。
評価の根拠を記録し、面談で伝える
評価の信頼性を高める最後のステップは、なぜこの評価になったのかを説明できる状態にしておくことです。評価の根拠を、メモや記録の形で残すようにしましょう。
たとえば、「ミス報告の整理と再発防止策を提案」「業務マニュアルを更新し、新人教育に活用」など、具体的な行動事例を短く記録しておくと、面談時にそのままフィードバックの材料として活用できます。
社員は「ちゃんと見てくれている」「評価の理由が明確だ」と感じ、納得感が格段に高まります。
このように、定性評価の客観性は制度の設計だけでなく、日常の観察・記録・対話によって磨かれます。評価者の主観を減らし、評価される側の納得感を高めることが、制度を「育成の仕組み」として機能させる第一歩です。
まとめ
成果が見えにくい職種の評価は、数字では測れない「支え」や「貢献」をどう見つけ、どう伝えるかが鍵になります。
結果だけに焦点を当てると、バックオフィスやサポート職の努力は見えにくくなり、評価が主観や印象に偏ってしまいがちです。
そのためには、プロセスを評価する視点、職務の目的を明確にする設計、貢献先で成果を捉える仕組みが欠かせません。
さらに、定性評価を主観で終わらせず、行動基準の明確化や複数の視点による確認、フィードバックの積み重ねを通じて、評価制度を「育成の仕組み」へと育てていくことが大切です。
評価制度は、社員を査定するための道具ではなく、組織が同じ方向を向き、互いの強みを発揮し合うための共通言語です。だからこそ、完璧な制度を目指すよりも、自社に合った使い続けられる仕組みをつくることが、何よりも重要になります。
もし、「うちの職種は評価が難しい」「制度はあるけれど運用がうまくいかない」と感じておられるなら、
ぜひ一度ご相談ください。
現場の実態に合わせた制度設計と運用の工夫で、評価が人を育て、組織を強くする仕組みづくりをお手伝いします。

